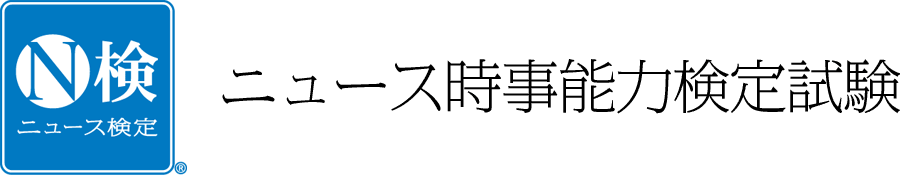N検のススメ
「正答のない問題」に挑戦しよう
今の若い人たちは、ゆっくり物事を考えるのをうとましがるように思います。「なぜ」という疑問を持たず、考える習慣が少ないようです。ニュース検定では、石油エネルギーの問題など、現代社会が抱える重要なトピックスを取り上げ、受検者がそのことについて考えるきっかけになることを狙っています。
就職にしろ、結婚にしろ、人生に正解はありません。大人は皆、正解がないことを知っています。正解がないから考えるのですが、今は「正解がないなら考えない」となっているようです。
私は将来、ニュース検定でも、「正解のない問題」を出題したらいいんじゃないかなと思っています。必死に考えて、自分のなかから答えを絞り出す。答え合わせはできませんが、社会のあり方を考え、自分ならどうするかを問うきっかけになるのではないでしょうか。
考えるベースとしての常識を身につけて
最近の社会では、秩序をとても重んじます。せっせと法律や規制を作りますが、それに従うのは社会全体のコストが増えることにほかなりません。社会のコストが増える、ということは、相互信頼がないということでもあります。
たとえば最近の医療の現場では、患者と医者の相互信頼が崩れかけているケースが増えている気がします。こういう世の中をどう変えたらいいか。それこそ正解などない問いなのです。
若い人にはニュース検定のような学習をきっかけにして、考えるベースとして常識を身につけ、社会の動きに常に「なぜだろう」という疑問と「ほんとうだろうか」という気持ちを持ち続けてほしいと思います。世の中の表層に惑わされず、ゆっくりとおおらかに物事を考えてください。
ニュースへの関心がよりよい社会を作る
情報過多が言われる時代です。でも日々、出来事が起こるのは仕方がない。頭の中でそれに適切に対処していくことは、現代人にとって重要な仕事です。現役の時はつい自分の周囲だけが大きく見えますし、引退後は関心自体が薄れてしまいます。多くの人がいわゆるニュースに適切な関心を持つことが、よりよい社会を作る基礎になるはずです。その意味でニュース検定に関心を持っていただけるとありがたいと思っています。
新間を読む習慣をつけるには
自分が興味のないことは知らなくていいと考える学生が増えています。彼らは半径5メートル以内の話題には強く関心を示しますが、広く社会に目を配ることには積極的でないようです。そうかといって新聞を渡し、「今日から新聞を読みなさい」と言ったところで読まないでしょう。まずは親や先生自ら新聞を読み、共通の話題になるような興味深い記事を選んで読ませてみてください。それから「この記事についてどう思う?」と質問してみたり、意見交換をすることから始めてみましょう。次に、一面下にあるコラムなど比較的まとまった記事を毎日読むのも少しずつ新聞が生活の中に入ってきます。コラムを読むことで、正しい日本語も学ぶことになります。
基礎を固めるために、ニュース検定の活用を
今、私たちは多様なメディアを利用できる環境にあります。中でも新聞は「世の中で起きていることの全体像がわかる」という大きな特徴をもっています。新聞を読み続けることで、出来事の軽重を判断する力や、変化する社会のどこに着目するべきかという相場観も身につけることができるでしょう。社会の中で自分が置かれている立ち位置を知るためには、新聞を読むのは効率的です。とは言え、言葉や熟語を知らなければ小説が読めないように、ニュースも基本的な知識やキーワードの意味を習得していなければ、全体像を理解するには至りません。基礎をしっかりと身につける方法として、ニュース検定を活用することは有効な手段と言えるでしょう。
教養とは「無用の用」を持つこと
最近の学生を見ていて感じるのは、短期的な成果に結びつく活動には一生懸命になるが、すぐには成果がみえない活動には冷たいということです。教養を身につけるということは、今すぐには役に立たないかもしれないけれど、長期的に自分の引き出しをたくさんもって、いずれ人生を豊かにするような「無用の用」を持つことです。それが長い時間をかけて人間としての魅力を増し、厚みのある人間性を育むのだと思います。未来を担う若者たちには「すぐに金になる」「勝ち組になる」といった視野の狭い目標よりも、自らの教養をじっくりと醸成してほしいと思います。
習い事の世界では、「免許を取ったら一人前」というわけではなく、習ったことを自分の血肉としてマスターして自由に使いこなして一人前となるといわれます。習い事と同様、検定試験も合格して級を取得することで技能や知識の向上意欲を高めていくという極めて日本的な知恵に結びついた仕組みではないでしょうか。ニュース検定においても級を取得することだけを目的とせず、身につけた知識を基礎として、自分で考え、判断できる良識をもてるようになってもらえればと願っています。
【プロフィル】
東京大学卒業後、1969年総理府入省。内閣広報室参事官、男女協同参画室長などを経て、98年女性初の総領事(オーストラリア・ブリスベーン)に。2001年内閣府初代男女共同参画局長。04年昭和女子大学教授となり、同大学女性文化研究所長、07年より同大学学長、16年より現職。
著書に『女性の品格』(PHP新書)など多数。
世の中のさまざまな事柄について自分の力で、情報を集め、疑問を持ち、考え、議論し、答えを出す学問の場、それが大学です。その結果、生きる力、つまり「教養力」が身につくのです。そのためには当然、今、生きている時代を知らなければなりません。新聞やテレビのニュース番組に日々、接して、日本や世界で何が起きているのか、正確な情報を幅広く身につけて深く考えるのです。大学生活を充実させるにはこの努力が不可欠です。大学生活を実り多きものにするために、受験勉強の合間にできるだけニュースに接するようにしておくといいでしょう。
※東洋大学では、早期入学決定者が大学の学びへの橋渡しとして入学前に公式教材で時事の基礎を学んでいます。また、経済学部では1年生全員が準2級を受検、社会学部では希望者が上位級を目指すなど、学生の時事力養成にニュース検定を活用しています。
場を乱さず、空気を読むこと?
何年も前から気になっていることがあります。「コミュニケーション能力」という言葉をよく耳にしますよね。略して「コミュ力」。就職試験でも企業側はこの能力を重視しているといいます。では、この「コミュ力」とは何でしょう。
若い人たちに質問すると「場を乱さない」とか、「周りの空気を読む」とかの答えがよく返ってきます。でも、本当にそうでしょうか? 自分の考えをきちんと相手に伝える。相手の話をよく聞く。そして、できれば一致点、共通点を探っていく……。それがコミュニケーション能力だと考えてきた私は少し驚いてしまうのです。
確かに集団の中で自分勝手に振る舞うのはいけない。ただし、最近は自分の考えを言わない(言えない?)人が増えているように思うのです。企業側が協調性を求めているのは確かでしょうけれど、経営者や採用担当者のみなさんに聞いてみると、やはり、自らの意見をしっかり言える人材を求めているのですね。
18歳から大人になろう。大人も大人になろう
これは、もう20年近く前の話です。ある若者たちの集まりで、親の仕事の都合で、中学生時代はドイツの学校で学び、帰国して日本の高校に通っている女子生徒から、こんな話を聞きました。
「ドイツの学校では、歴史の授業などで、手を挙げて自分の考えを言わないと良い成績をもらえなかった。ところが、日本に帰ってきたら、自分の意見を言うと『変わり者』だと思われてしまう」
中でも政治の話なんてしようものなら、周りから孤立してしまう、と彼女は続けました。
実は若い世代だけではありません。男女を問わず、大人も政治や社会の問題について、会話することが少なくなっているように思えます。きっと、そんな話題を持ち出すと、「場を乱す」「嫌われるかもしれない」と恐れているに違いありません。
ご存じのように、選挙の投票年齢がかつての20歳から18歳に引き下げられてから、だいぶ時間が経ちました。私はかねて「18歳投票を」と熱心に報道してきた記者の一人です。引き下げを機に、高校の教育現場で「今の政治」を学ぶ「主権者教育」が必要ではないか――と初めて提唱した総務省の有識者会議にも委員として加わりました。
しかし、この引き下げ問題が国会でテーマになり始めた頃、当事者である高校生から、しばしば聞いたのは「私たちまだ大人じゃないから選挙権なんて要らない」「私たちは政治に関心があまりないから選挙権を持つ資格がない」といった話でした。これまた驚いた記憶があります。
社会全体の問題、とりわけ政治の話は難しそうで、縁遠いものだと考えているのでしょう。これまた若い人たちだけではなく、大人もそう感じている人が多い、というか、増えているのですね。
若い世代の選挙の投票率が低いと再三言われますが、低投票率は今、全ての世代に広がっています。「投票に行ったことがない」という若い人に聞いてみると、その親も行かないという人が多いのです。私は「これも一種の格差の固定化につながる」と言ってきました。
選挙は私たちが政治にかかわる最大の機会です。政治家に「お任せ」しているばかりでは大変なことになる。それはみなさん、お分かりだと思います。だから、18歳投票が始まったころ、私は毎日新聞の自分のコラムやテレビの報道番組で「18歳から大人になろう。ついでに大人も大人になろう」と呼びかけたものでした。
政治はそんなに難しい話ではない
政治を難しく考える必要はないのです。例えば、若い人たちの関心事で言えば、教育費がいくらかかるかとか、奨学金がどうなるかとかを決めるのは政治です。自分が高齢者になった時、年金はどうなっているのか。不安な人もいるでしょう。もちろん、それも政治、つまり時の内閣や国会、政党が決めるのですね。
そうした身近な問題から話題にしてみる。そして勇気を出して「最近の〇〇首相ってどうよ?」と意見を交わしてみる。そうすることで自分の考えがまとまっていくのではないでしょうか。相手は違う意見かもしれない。反論されるかもしれない。けれども、違う意見もじっくり聞いてみる。それで自分の考えが変わるかもしれない。世の中にはさまざまな意見があるのですね。それを知る良い機会にもなる。そう。そうした会話ができることこそ、本当の「コミュ力」というものだと思うのです。
会話の材料となるのが、さまざまな情報です。情報源は、新聞、テレビ、インターネット等々、いろいろあります。もちろん私はもっと新聞を読んでもらいたいと願っていますが、何より大切だと思うのは、その情報をもとに会話、議論を重ねることです。それが、その情報が正しいのかどうか、吟味することにもなります。
ニュース検定は、そうした「コミュ力」を身につけるためのツールです。政治や世界の動きも含めて、自分の周りで起きている事柄を、自分が確認するきっかけになります。 「おじさん」の私も、これまで関心のなかった分野にも興味を持つのはとても楽しいことだなあ、とますます感じ始めているのです。みんなで議論する場を作っていきましょう。私はどこへでも出かけていきます。